園長への道のり〜公立から企業型、そして認可園へ〜
当時21歳の私は倍率125倍(1000人中8人合格)の難関公務員試験に合格し、公立保育園に勤めたのが保育士としての始まりだった。
公立園では充実した毎日を過ごしていたが、転勤の多い夫と一緒になったため公務員を退職し専業主婦となった。周りの同期には辞めるなんてあり得ないと言われたが、保育士だからこそ自分の子育ては全スキルを投入して行いたい!と思っていたので後悔はなかった。
その間2人の子育てに没頭し、保育スキルを駆使して満足の行く子育てをやりきった。
2人目が働いていいよと言うまでは家にいようと思い、2人目が小学2年生になってからは毎年働いてもいい?と聞いていたが、毎年だめと言われていた。
それが突然、小学5年生のもうすぐ11歳を迎える頃、まさかの子どもの方から働いていいよ、と言われた。
10歳を節目に子どもが成長する話はよく聞くが、なるほど、子どもなりに母のことを考えられる様になったということか。最近は2分の1成人式とは言わなくなったらしいが…
そして15年ぶりに保育業界へ復帰。
公立でパートから始めるつもりも空きがなく、それなら最悪?と言われる株式の企業型保育園に勤めてみようと思い立った。
そこは保育と呼ぶにはあまりにも拙い内容で、子どもを遊ばせることなく、ずっとおんぶしたまま作業する保育士。株式の悪口ばかり言う保育士。終いには私たち全員辞めるから辞めたほうがいいよ、とまで言われる始末。
見るに見かねて社長へ直談判。
公立のような保育がしたい!環境を整えたい!
いいよ、でもパートのままでは無理だから正社員になって、との社長の言葉で園長となった。
そして気がつけば採用から職員教育から行政対応までこなすようになっていた。
保育園がだんだん安定してくると企業型保育園の限界を感じるようになっていった。
園児がなかなか集まらず毎月赤字状態でいつ潰れてもおかしくない状況。
それでもここが潰れたら困ると言ってくれる保護者がいる。
時は待機児童が多く株式の保育園がどんどん作られている頃。
そうだ、今のうちに潰れないよう、まずは認証にしてしまおう!
そしてまたもや社長へ直談判。
今回もいいよ、と。
そして、あれよあれよと認証から認可にまですることができた。
ただ保育業界に興味のある会社ではなく、1園しか持っていなかったため、認可園の園長としてのスキルをもっと磨きたい、でもここでは無理だと思ってしまった。
そして次のステージへのチャレンジ、大手企業への転職を決意した。
大手企業での10年、園長が担った役割
開園の舞台裏
時は株式が参入を開始して、待機児童対策のため行政と共にどんどん新園が作り上げられている時期。
そんな折なので大手企業での保育は開園から携わった。
採用や園内の設備については本社がすべて用意してくれていた。さすが大手!
前の会社のようなゼロから作り上げるものではなかったので、職員育成と保護者対応が最初の大仕事だった。
ただ開園日は迫っているというのに職員が集まらない。
どうなるのだろうという不安と大手だから何とかしてくれるだろうという楽観的な気持ちの中、いよいよ開園日当日を迎えた。
初日は入園式。
園児と保護者は期待に胸を膨らませてにこやかな表情で園内へ入ってきた。
一方、裏では職員数がまだまだ不足している状況の中、突然、栄養士が「話と違う!自分は辞める!」と口にして去っていく始末…。一週間分の発注だけお願い!と頼み倒してなんとか給食は乗り切った。
そしてその後も相変わらず職員は不足していたが、開園のため園児数がMAXではなかったのと、慣らし保育で始めの2週間が短時間保育だったので何とか乗り切ることができた。
保護者対応〜信頼関係の構築とモンスターペアレント〜
職員が揃い始めてようやく保育に力を入れられると思い始めた頃、次の問題がやってきた。
保育者なら一度は悩む保護者対応だ。
カオスな保護者会と違和感
最初の保護者会から前の園の時とは何だか違う客層だな…と少し違和感は感じていた。
というのも、3歳クラスの自己紹介で子どもの家での様子を教えてもらったのだが、「うちの子は動画が大好きで家で何度も見ています。特にとかげが虫を丸呑みするのが大好きなんです!」と堂々とコメントする保護者。
周りは絶句。
特に子どもの姿に困っているという様子でもなく当たり前のように話す保護者の姿が印象的だった。
そして、開園して初めての保護会だったので、保護者がお互いの子どもの顔も分かるようにと親子参加型にしたのだが、これが間違いだった。
このクラスの子どもは多動が多くじっとしていられず、部屋の中を走り回り、大声を上げる始末。
担任は大声を張り上げるも、自分の声が届かず、とうとう泣き出してしまった!
泣き出す担任を慰める保護者、我関せずと携帯をいじる保護者…カオス
そして私の不安は的中して、このクラスの保護者と園児が大変なことに…!?
信じられない「ご意見」の数々
なぜか人が集まると似たような人が集まる。
3歳クラスの保護者はひとり親も多くゆとりがない、それ故に自分のことが最優先、そんな保護者が多いクラスだった。
そして当然子どもたちも自分の感情を受け止めてくれない親の元で育っているので、感情のコントロールが苦手な子どもが多かった。
本当にたくさんの苦情(現場ではご意見という)があったが、びっくりするようなご意見もたくさんあった。
私の保育人生の中でもランキング入りする苦情を以下に紹介する。
ある日の夕方、母親から園に電話が入り酔っ払った様子で「今、手が離せなくて迎えに行けない!園の前のファミレスに居るから連れてきて!」…丁重にお断りすると更に激怒。
そしてその日の夜、一升瓶を抱えて酔っ払った母親が園に乗り込んで来た。
自分が如何に大変か、子どものこと、仕事のこと、夫のこと、延々と2時間。
時間は夜の9時…。
さすがに警察を呼ぼうとしたが、本人が職場の上司を呼んで欲しいと訴えるので、電話して連れて帰ってもらった。
ある時の保護者会では行事の日程が仕事で行くことが出来ない、行事は保護者のためにあるものだから行ける日に開催してくれないと意味がない、と堂々と発言する保護者。
この時は隣の人にもどうですか?と順番に全員聞いていくと、自分勝手な意見だと気がついたのか、一周回って来たときには「別に日にちを変えてほしい訳では無い…」と言い換える始末。
こんな自分勝手なご意見を言ってくる保護者に共通するのは、「保育園は保護者のためにあるものだ!」と心から思っているところだ。
そして保育者は保護者の意見に耳を傾けるのが当たり前と思われ、普段のストレスをぶつけられる。
今で言うカスハラ。
あの頃はハラスメントに対する意識もまだまだ低く、職員の心のケアに悩む日々だった。
担任と保護者を守るために
開園から3年目、心配していたことがついに起こった。
モンスターペアレントの言動に耐えきれずに主任が突然来なくなってしまったのだ。
そして急遽新しい担任に変わったのだが、ある日、何度も同じ子どもに噛みつかれた1歳児のクラスの父親から電話があり「その子どもを訴える!」「無理なら園を訴える!」と罵声を浴びせられてしまった…当然、担任は号泣。
このままでは新しい担任も辞めてしまう…。
実は何度も噛みついた子どもは発達が心配な子どもで、視覚的な刺激に弱く、視界に人の姿が入ると噛みついてしまうことが日常茶飯事だった。
しかし、噛みついた子どもの保護者にすら発達についてフィードバック出来ていない状況下で、相手側の保護者に事情を言うことは出来ず、ひたすら謝罪するのみだった。
こちら側の未熟な対応が保護者をモンスター化しているのか、地域柄なのか、今の時代のせいなのか、とにかく藁をもすがる思いで当時役所が開催してくれた保護者対応の研修に担任と共に参加してみることに。
そして、そこで保護者対応の考え方を根幹から変えてしまう考え方に出会うことになろうとは…
藁をもすがる思いで参加した「保護者対応研修」
研修のタイトルは「対応に苦慮する保護者対応」
講師は横浜国立大学の井上果子先生。
まず保護者をタイプ別に分類し、そのタイプに応じた対応方法をレクチャーしてくれた。
そして事前に提出していた現場での困り事に答えてくれた。
「保護者のタイプ分け」という衝撃の出会い
タイプ別に分ける、まずその考え方が目からウロコだった。
私はこれまで保護者に対して真摯に耳を傾け、丁寧に答えることで信頼関係を築いてきた。
しかし、この園では最初は喜ばれたが、どんどんご意見がエスカレートしていき、とうとう答えることが難しい旨を伝えると保護者の態度が豹変するという事態になっていた。
タイプ別と聞いて、今まで対応に苦慮する保護者のために多大な労力と時間を使い果たし、職員共々に疲弊していたが、それは園全体からしたら極一部の保護者にすぎないことに気付かされた。
感情的にならず、客観的に向き合う
感情的にならず対応するためにも、まずはその保護者が対応に苦慮する難しい保護者であるとを認識すること。
そして、どのタイプなのかを知ること。
ここを抑えるだけで精神的負担が大きく減少する。
苦情の第一窓口は職員であることが多い。
最初に対応した職員が嫌な思いをしたら、まずはその保護者がどんな態度だったかを見える化してタイプ別に分類し、複数の職員と話し合ってどう対応するか決めるようにした。
保護者のタイプによっては真摯に耳を傾けることがいいとは限らない。
特に脅したような口調で言ってくる場合は、毅然とした態度でこちらも大きな声で言う必要がある。
これらは人が好きな保育士からすると苦手な対応かもしれない。
ただ、今の世の中、一定数の対応に苦慮する難しい保護者が存在するのも事実であるため、客観的な対応が求められるのかもしれない。
障害児増加と向き合った日々
職員の心が軽くなった保護者対応
保護者をタイプ別に分類し始めて、職員の気持ちが前向きに変化した。
難しい保護者へは近づきすぎず出来ることと出来ないことをはっきり伝える。
そうでない保護者に対しては今まで通り傾聴する。
どう対応したらよいか分かると自分のせいで上手くいかなかったのでは?と責める気持ちが減って、その分前向きになれたのだろう。
現代社会が突きつけた、もう一つの問題
保護者対応が上手くなってくると次の問題が浮かび上がってきた。
それは保護者対応の難しさの裏に障害児という問題が隠れている場合だ。
保育園が担う、現代の子育て
保育園は0歳児から入園できる。
そして預かり時間が平均10〜11時間と長い。
3歳までに人間としての基本的な活動を習得すると思えば、保育園児はほぼ保育園の生活で育つと言っても過言ではない。
昔は普通にあった公園や近所の共有スペースで子育て世代がお互い様と思いながら関わり合って、喧嘩の仲裁をしたり他人の価値観を知ったり、そんな親の姿を子どもも見て学んでいた。
親子共に育ち合っていたのだ。
しかし共働きがほとんどとなった現代で、そんな姿はほぼない。
すると保育園での価値観が全てであり、保護者も子どもが分からないが故に保育園に依存する。
何も問題がない場合はこれでも保育園生活の6年間くらいなら何とかなる。
現場が直面する、障害児という現実
問題は子どもが成長するにつれ、他者との関わりが上手くいかない場面が増えていった場合だ。
攻撃性がある子ども、ない子ども
保育園で考える障害児については大きく分けて2通りある。
他者や自身に対して攻撃性がある場合とない場合だ。
噛みつき・引っ掻き…クレームの悪循環
攻撃性がある場合は集団でお預かりしていると、クレームに発展しやすい。
普段から他の子どもと関わる我が子の姿を見る時間が少ない保護者からすると、状況が全くわからず、我が子に付いた傷だけが目に入りやすいからだ。
1〜3歳くらいは言葉が未熟なため自分の思っていることを相手に上手く伝えられず、噛みつきや引っ掻く行為が多くなりやすい。
ただ、これは事前に保護者へ子どもの成長過程で目にしやすいことであることを伝えておけば、大きなクレームになることは少ない。
こじれる場合は同じ子どもからの噛みつきや引っ掻きが頻繁に発生し、力加減も難しいのか流血するほど深い傷にしてしまうような時だ。
このような時、保育者はまたクレームになるのでは、と大きな声で注意する場面が増えるようになる。そして室内はその声の大きさで緊張した雰囲気になり、更に噛みつきが起こりやすくなる。
悪循環だ。
子どもにしてみれば自分の気持を処理する方法として、その手段に出たに過ぎない。
よく「◯◯ちゃんが痛くて泣いているよ。ごめんねは?」と仕切りに謝らせようとする保育者がいるが、この場合に限っては相手の思いに気付く段階ではないため、まずは自分の気持ちに気付かせることが先決だ。
通常、日々のやり取りの中で徐々に自分の気持ちを理解し相手の気持ちに気付けるようになるのだが、障害が絡むとそうにはいかない。
暴れる子ども、職員3人がかりの対応
保護者が障害を認めずに成長した5歳児では、自分で気持のコントロールができず、何かが気に障ると突然暴れ出して手が付けられないことがよく起こった。
ひどい時は保育室の玩具だけでなく机や椅子も投げ飛ばすので、他の子どもたちを避難させ、保育者3人がかりで止めることもあった。
増加する「過敏な子ども」という現実
一人でいる場合は他のこどもが遊んでいる場面を見て自分もやりたいとか、それは嫌だとか、視覚的や聴覚的に邪魔だ、といったこともないので攻撃性は見られない。
一人っ子の場合、親が気付かないのも当然だ。
そしてこういった過敏な子どもは、ここ数年で10人に1人は見られるようになってきていた。
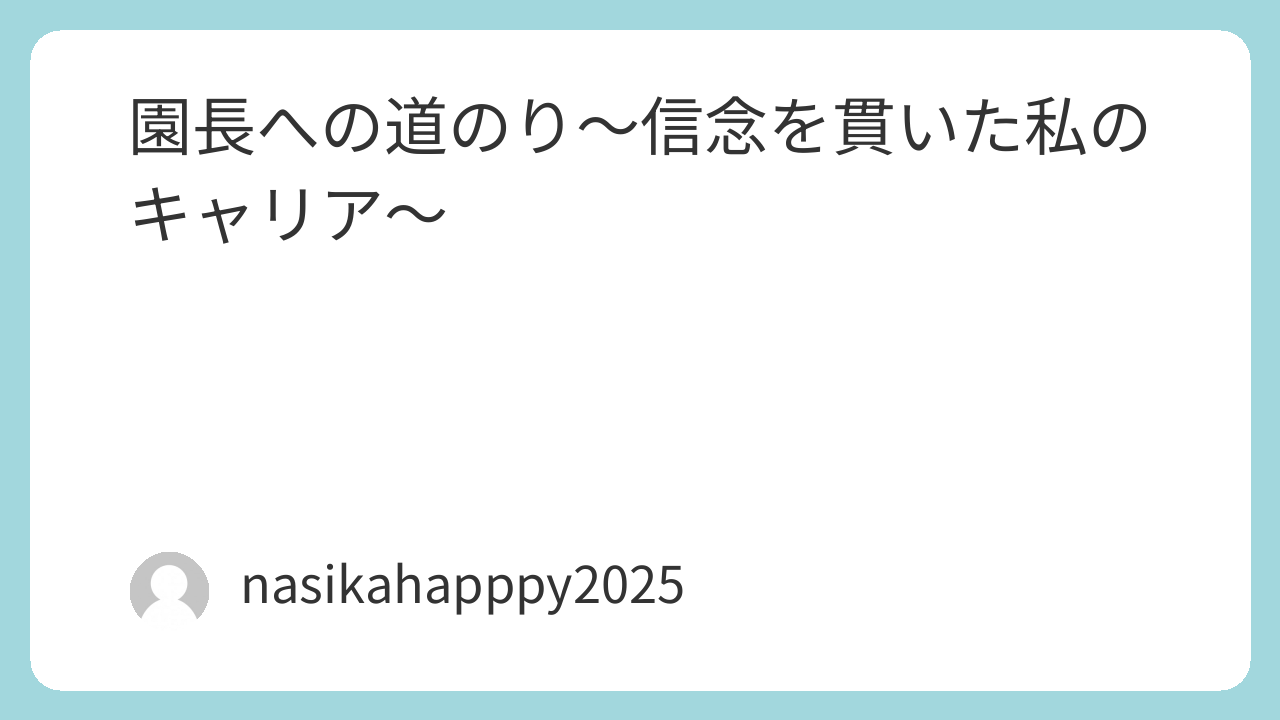
コメント